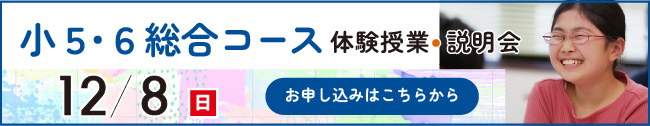昨今の中学、高校、大学入試では、教科の知識だけが問われるのではなく、知識の活用を前提に論理的思考力・判断力・表現力が問われる問題も増えています。つまり、「覚える」だけでなく、知識を「考えて、活かす」学習が求められているということです。さらに、公立中高一貫校受検では、教科横断型の試験に対応する力が必要です。
親子が笑顔になれる"幸せな受験"を実現



公立中高一貫校の受検で扱われる「適性検査」では、設問に先立って展開される説明文や会話文を読み、統計資料や図を参考に、その中にちりばめられている問題のポイント、あるいはそのヒントを抽出し、すでに持っている知識を組み合わせて解いていきます。
作文… 与えられた文章・図表の要旨をつかみ、自分の体験や社会問題への考えを述べる問題が出されます。
資料読み取り… 私たちの身の回りの事象(料理やSDGsなど)を題材に、統計・実験・観察を基に踏み込んで考え、自分の判断を説明する問題が出されます。
数理的思考力… 立体図形・平面図形・論理的思考をはじめとした、粘り強く考え抜く必要がある「難問」といってよい問題が多く出題されます。

公立一貫校受検では、志望校に特化した「適性検査」の具体的な対策を始める前に、基礎学力をしっかりと固め、考える楽しさを味わう経験を積むことが重要です。
また、小学校から提出される「報告書」が点数化されていることから、しっかりとした学校生活を過ごすことも大切です。
「やらされる勉強」ではなく、「考えることの楽しさ」や「自由に表現し、相手に伝えることの喜び」を土台として、自由な発想を大切にしながら、自分の言葉で文章を書き、難問にも挑戦する―。公立中高一貫校受検コースでは、そうした学びを行います。




鍛錬を通じて、適性検査で求められる力を身につける時期です。 「理系」「文系」という授業枠の中で「読解力・作文力」「資料 分析力・記述力」「理数的論理力・思考力」の3つの軸で、学力を磨いていきます。また、GW特訓、サマーチャレンジといったイベントを通して「受検生」としての意識を高める、鍛練の場を設けています。


「合格のため」の学習に入ります。志望校の適性検査問題を用いた実戦演習を行います。公立中高一貫校の入試は、厳しい「時間との勝負」という側面も持っており、本番さながらに時間を測りながらテスト演習し、その後解説を行います。その際に作成した答案は一人ひとりにフィードバックを行い、きめ細かい指導で得点力アップを目指します。
公立受検頻出の社会的・理科的テーマも織り込み、新聞記事や図解資料を基に情報・知識を学びながら、考えを発表し合い、文章にします。小5合科授業で培った「考えることを楽しむ」姿勢を大切にしながら、9月以降の過去問演習につながる記述力を身につけていきます。これはグループ面接がある学校においても、非常に有効です。